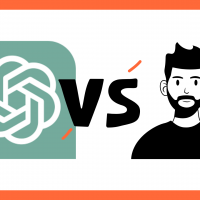誰かと生きるということ 「老ナルキソス」の問い
五十年という時間が流れると、世の中は変わっていく。たとえば、1973年に「手のひらサイズの道具で、いろいろな人とコミュニケーションをとることができる」と言っても、夢物語として扱われたことだろう。
同じように「男性同士の恋愛がテレビやドラマで扱われて、人気のコンテンツになる」、「自治体が同性カップルに対して、パートナーであることを証明するようになる」といった話をしたら、どうだろうか。
「老ナルキソス」は、そんな時代の変遷を喜寿の絵本作家山崎と、25歳のウリセンボーイ、レオとの交流を通して、二人の間を結ぶ世代であり、バイセクシュアルでもある東海林毅監督が描いていく。
あらすじ
ゲイでナルシストの絵本作家・山崎(田村泰二郎)は、老いによって自分の容姿が衰えていくことに耐えられず、作家としてもスランプに陥っていた。ある日、ウリセンボーイのレオ(水石亜飛夢)と出会い、その若さと美しさに圧倒される。会話の中で、レオが自分の代表作を心の支えにして育ったことを知ったことをきっかけに、自分以外の存在に対して初めて恋心を抱く山崎。そして、二人の交流が始まる。
ゲイカップルの過去と現在と未来
映画の中では、いくつもの対比が提示される。たとえば、喜寿の山崎とレオの恋人である隼人(寺山武志)だ。
山崎はレオをつなぎとめるため、ひとりで養子縁組の手続きを進める。同性カップルが家族となるために昔から使われてきた制度だが、世の中にパートナーであることを示すものではない。
一方で、レオとの関係を祝福してくれる家族を持つ隼人は、パートナーシップ制度の利用を無邪気にも見える態度でレオへ迫る。こちらは公的にパートナーであることを証明するものだ。しかし、法律的な面では、まだ充分な保護を得られるものとは言えない。
隼人のプロポーズに対して、レオはその気持ちを受け入れながらも、制度を前にして踏み込めない。
彼は訴える。母子家庭で育ち、親から充分な愛情を与えられなかった自分には「家族」というものがわからないと。
だが、そもそも男女の夫婦像がレオと隼人にとっての家族像になるのだろうか。むしろ、必要なのは「家族」になったゲイカップルのハズだ。しかし、そういった存在は作品中には描かれない。
それは「現在の日本には、見える場所にまだ確固たるモデルがない」ということを暗示しているのだろう。
だが、それは同性カップルに未来がないということではない。たとえば、結婚したカップルにインタビューをするテレビ番組で同性カップルの出演が話題になった。
また、2019年にドラマ化された漫画、『きのう何食べた?』では、中年のゲイカップルの姿が描かれた。
道がない場所にも生き物がその場所を通れば獣道ができ、やがては道路になっていく。同じように、モデルはこれから隼人とレオのようなカップルによって作られていくのだろう。
とはいえ、まだようやく道らしきものができたという状況だ。そんな状況では、先人が歩んできた道が参考になることもある。
「老ナルキソス」は作品を通して、いくつかの人生を語りかけてくれる。その中に、同性カップルも含めた全ての人が人生を幸せなものにするための問いが隠されているかもしれない。